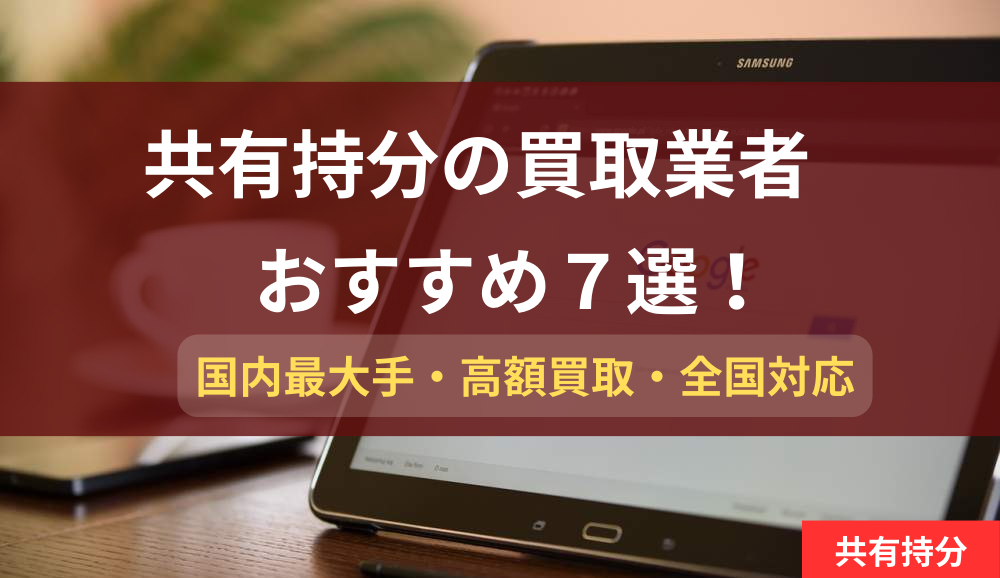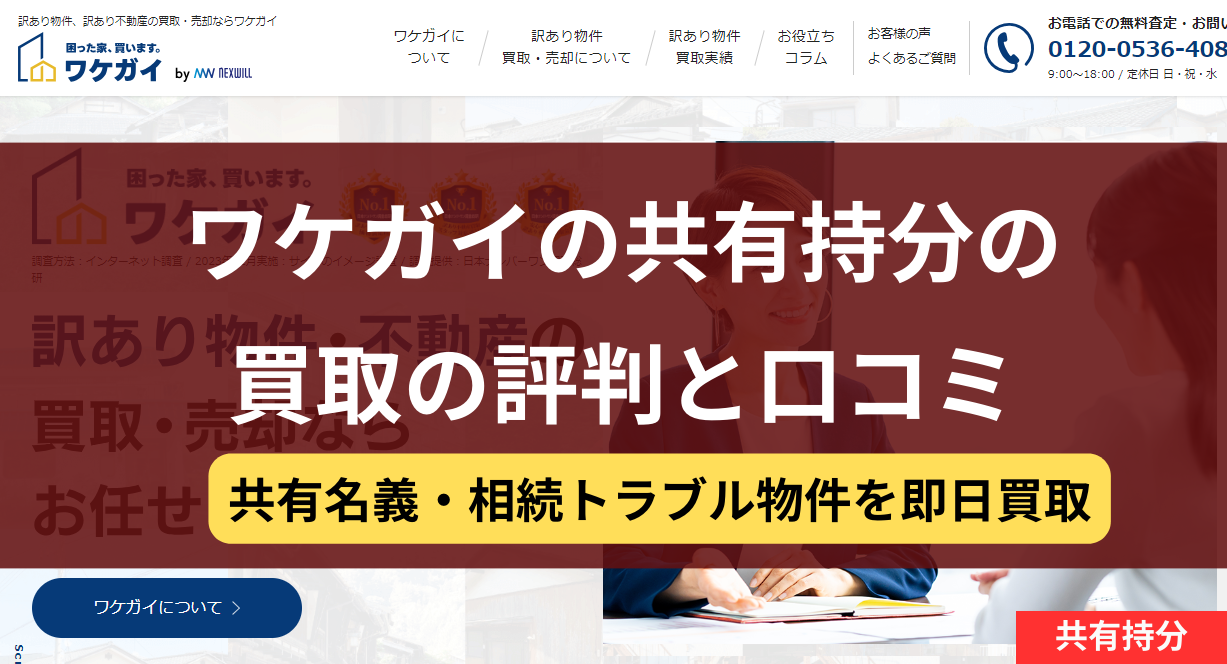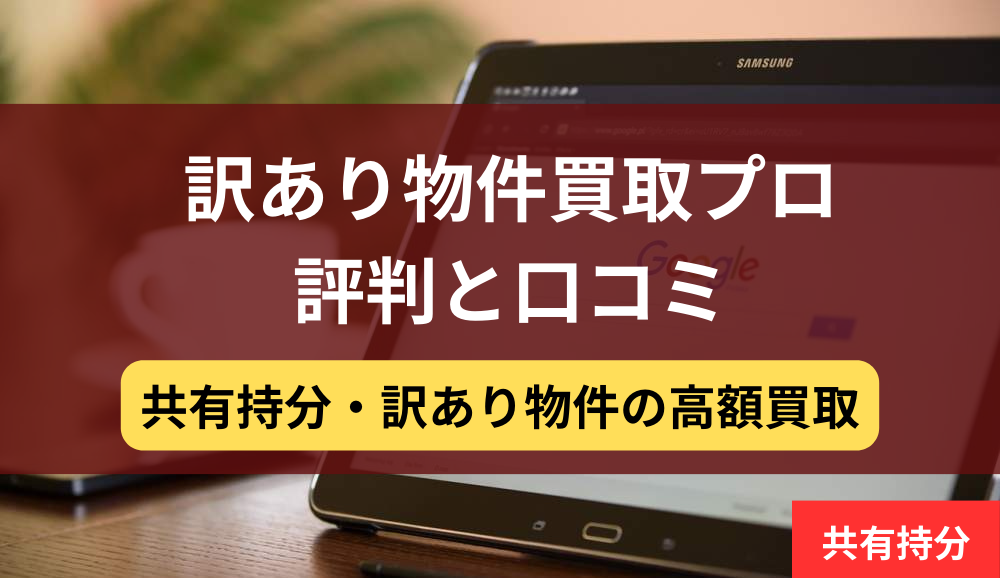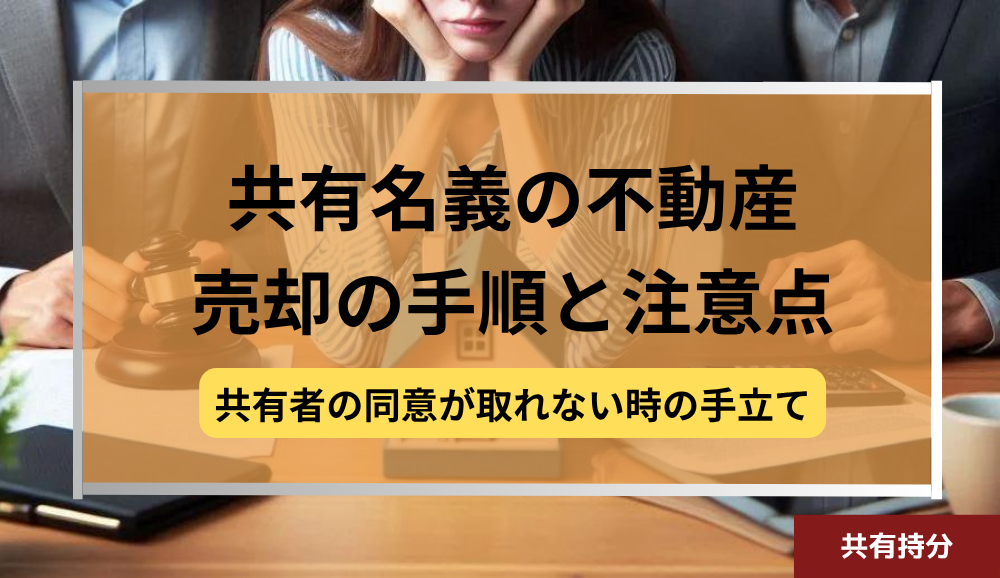
不動産を共有名義で所有している場合、売却の手続きには他の共有者との協議や同意が必要となります。複数の名義人が関わるため、スムーズに売却を進めるためにはしっかりとした準備と理解が求められます。
共有名義の不動産の売却は手続きが複雑に感じられるかもしれませんが、適切なステップを踏むことで、安心して不動産の売却を進めることが可能です。
この記事では、共有名義の不動産を売却する際の手順と、気をつけるべき重要なポイントについて詳しく解説します。
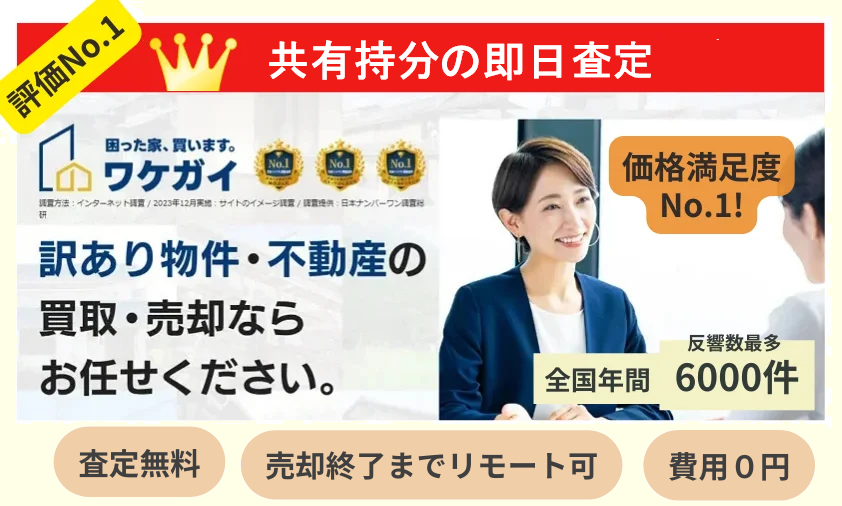
ワケガイの査定は無料で買取金額を提示、買取に至らなかった場合も費用は一切発生しないので安心。売却終了までリモート対応も可!
査定無料
関連記事:
共有持分の不動産の買取業者おすすめランキング【2026年】
共有名義の不動産の売却
共有名義とは一つの不動産が複数の所有者によって共有されている状態を指します。
多くは相続で、きょうだいなど複数の相続人が実家や両親の保有する不動産を共有名義とすることがあります。
他には夫婦で不動産を購入する時に共有名義にするということも普通に行われますが、それぞれの意見が一致しない場合に売却が困難になることが共有名義の不動産のいちばんの問題点となります。
不動産の売却ができる場合と、できない場合の両方を見ていきましょう。
関連記事:
共有持分とは何かわかりやすく解説
共有名義の不動産の売却の手順
共有名義の不動産売却の手順はおおむね下のように行われます。
1 売却の同意を得る
共有名義の不動産を売却するには、共有者全員の同意が必要です。基本的には全員の合意が得られなければ、売却プロセスを進めることができません。
そのため、事前にしっかりと話し合いを行い、売却に対する理解を得ることが重要です。
2 不動産の査定と価格設定
売却に向けて、不動産の市場価値を正確に把握するために査定を行います。
専門の不動産会社に依頼し、査定額を元に売却価格を設定します。この段階で、共有者全員が納得できる価格設定が求められます。
3 売却契約の締結と必要書類
売却に合意が得られたら、買主との間で売却契約を締結します。
この際、共有者全員の署名が必要となります。また、登記簿謄本や印鑑証明書、身分証明書などの書類が必要になるため、事前に準備しておきましょう。
4 売却後の手続きと税金
売却後には、売却益に対して譲渡所得税が発生する可能性があります。
売却益が発生した場合、各共有者の持分に応じて利益が分配され、それに基づいて税金が課されます。
税金の負担を考慮し、事前に税理士に相談することをお勧めします。
共有名義の不動産の売却における注意点
共有名義の不動産を売却する時の注意点もお知らせします。
税金の負担と分配
不動産売却時には譲渡所得税がかかります。
利益が出た場合、各共有者の持分に応じて課税されるため、税金の負担を理解しておく必要があります。
税額が大きい場合は、事前に税理士に相談して節税の方法を検討するのも一つの手段です。
売却による利益の配分
売却後の利益は、共有者の持分割合に応じて分配されます。
利益の配分に関する合意が事前にない場合、トラブルが生じることがあります。売却前に、利益の分配方法を明確にしておくことが重要です。
トラブルを避けるためのポイント
共有名義の売却では共有者間で意見の相違が発生しやすいため、事前に詳細な話し合いを行い、売却の方針を明確にしておくことが大切です。
さらに、専門家のアドバイスを受けることで、法的トラブルを未然に防ぐことができます。
不動産会社の選び方
共有名義の不動産を売却する際には、信頼できる不動産会社を選ぶことが重要です。
不動産会社の実績や評判を確認し、経験豊富な担当者に相談すると、安心して売却を任せることができます。
また、複数の会社から見積もりを取り、比較検討するのも良い方法です。
不動産会社を選ぶ時も共有者全員の意見を考慮に入れて、同意が取りやすい不動産会社を選ぶことも大切です。
共有名義の不動産が売却できない場合
共有名義の不動産は全員が一致して同意の上で売却をすることが必要となりますが、状況が変わったり、所有者の意向によっては同意が取れない場合があります。
また、相続によって生じる共有名義の不動産には、何世代にもわたって多人数での共有名義となっている不動産も少なくありません。
共有名義の不動産が売却できない場合についてみていきましょう。
共有者の同意が得られない場合
共有名義の不動産は共有名義の不動産を売却するためには、共有者全員の同意が必要です。
1人でも反対する共有者がいると、不動産の売却を進めることができません。
特に相続で取得した不動産や離婚後に残った不動産の場合、共有者の意見が一致しないことが多く、売却の合意が難しいケースがあります。
差し押さえや抵当権が設定されている場合
共有名義の不動産の中に、共有者の1人の債務が原因で差し押さえが行われている場合や、抵当権が設定されている場合、そのままでは売却ができません。
差し押さえが解除されるか、抵当権が抹消されるまで売却手続きを進められないことがあります。
共有名義人の1人が認知症や判断能力を欠いている場合
一般的な不動産の売買と同じく、共有者の中に判断能力がない人がいる場合、その人の代理人(成年後見人など)を立てなければ売却の同意を得ることができません。
成年後見制度を利用して代理人を選任する必要がありますが、その手続きには時間がかかることが多いため、売却プロセスが遅れることがあります。
共有名義の不動産を売却できない時の手立て
共有名義の不動産が、全員一致で売却ができない場合、合意がどうしても得られない場合は、法的機関を通して同意を得る方法と訴訟と持分売却の2つの方法があります。
1. 調停
調停とは、第三者(調停委員)が紛争の当事者間に入って、話し合いを進め、合意形成を促す方法です。日本の家庭裁判所や民事調停委員会などで行われることが一般的です。
調停委員は当事者の双方から信頼される中立的な立場で、双方の意見を聞きながら解決案を提示します。
プライバシーは守られますが、調停自体には強制力はありません。調停委員が示す解決策を基に双方が合意すれば、裁判所で確認された合意書として効力を持ちます。
何より第三者が間に入ることで、解決に至る可能性は高そうに思われます。
2. ADR(Alternative Dispute Resolution)
ADRは、裁判を避けるための紛争解決手段の総称で、調停もその一部です。裁判所を利用せず、専門の第三者(調停人や仲裁人)が関与して、双方の問題を解決することが目的です。
裁判よりも迅速かつ低コストで問題解決を目指す方法です。
ADRでは、調停人や仲裁人が問題解決のために介入します。調停の場合、双方が話し合いを行い合意を目指しますが、仲裁の場合は第三者が解決案を決定します。最終的に合意書が作成され、合意を得た通りに売却が行うことが考えられます。
3.共有物分割請求
上記の2つは裁判を避けるためのおすすめの方法ですが、解決策がより明確に示される裁判を選択するのもよい方法です。
共有名義の裁判は共有物分割請求と呼ばれます。
共有物分割請求とは、共有名義の不動産を所有している複数の共有者が、その共有物を分割したい場合に行う法的手続きです。
土地などを分泌して文津する「実物分割」のほか、 「換価分割」という名称となり、共有物である不動産を売却して対価を得たい場合の方法は、これらの形での合意を目指すことができます。
共有名義の不動産の裁判の手順
共有物分割請求の裁判は、家庭裁判所または民事裁判所で行われます。専門家(不動産鑑定士など)による評価が必要となる場合は、調査に数カ月の日数がかかることもあります。
裁判所は調停の機会を設け、共有者間で合意を目指します。または裁判所が和解案を提示し、共有者同士がその案を受け入れることで、裁判を終結させることも可能です。
もし調停や和解が不成立の場合、裁判所は最終的に判決を下し、共有物の分割方法を決定します。判決が下されると、その内容が法的に効力を持ちます。
特に換価分割が選ばれた場合、その不動産は売却され、売却益が共有者間で分けられる結果となります。
訴訟にはデメリットも
訴訟のデメリットは時間と費用がかかることです。また、場合によっては自分の思い通りにならないこともあります。
確実に売却を目指すのであれば共有持分の売却を行えば、相手の同意が不要なままで自分の持分のみを売却して、売却代金を受け取ることができます。
共有名義の不動産は全員一致で売却をするのが望ましいですが、どうしても売却ができずに塩漬けになっている不動産は共有持分の売却を検討してみてください。
※同意が取れない場合の共有持分の売却については下の記事を
関連記事:
共有持分の売却は他の共有者の同意は不要 不動産全体と持分の違い
まとめ
共有名義の不動産を売却する際は、共有者全員の同意を得ることが最も重要です。
また、事前に売却に関する手順や税金について理解しておくことで、スムーズに手続きを進められるため、こまめな情報の共有も大切です。
売却に関する書類や契約内容を明確にしておけば、安心して売却プロセスを進めることができます。
兄弟間や身内の場合で関係が良好であればそれほど神経質になる必要はありませんが、離婚時の売却や事業用の共有名義の不動産の売却の時にはきちんとした売買契約が行えるように入念に準備をすることが大切です。
▼共有持分の買取最大手▼

- 不動産高額買取⇒価格満足度Top
- 共有持分の業界最大手
- 買取率ほぼ100%
- 査定無料・全国対応
- 売却終了までリモート対応可
査定・相談無料
関連記事一覧:
共有名義の事故物件が売却できる買取業者おすすめ3選!