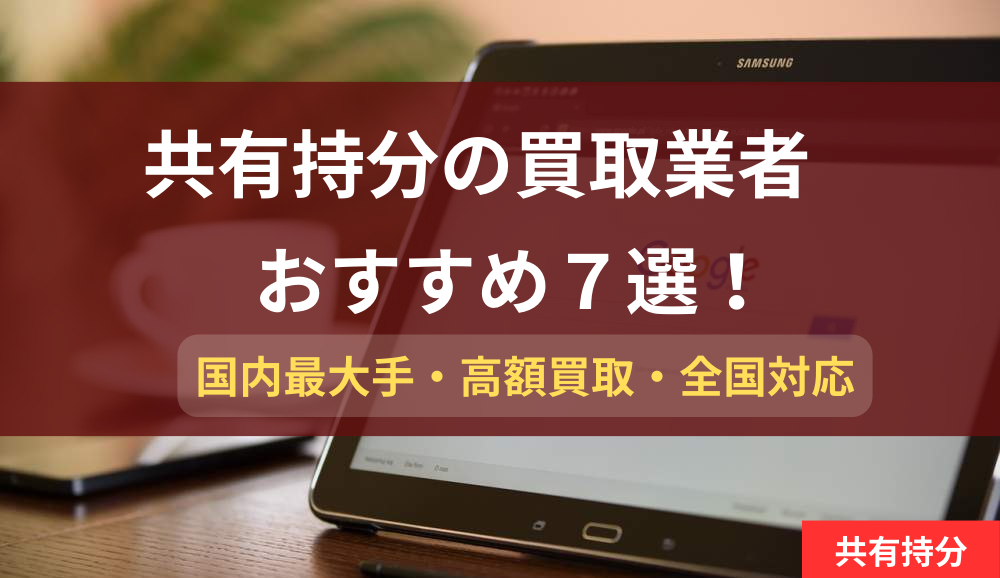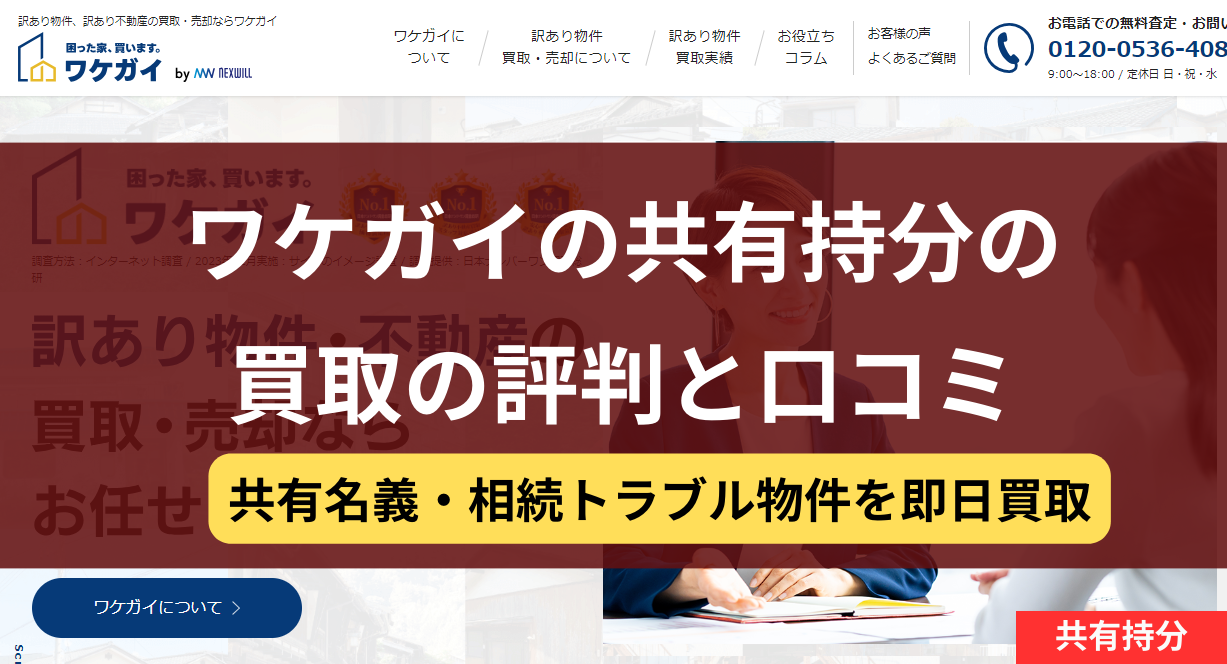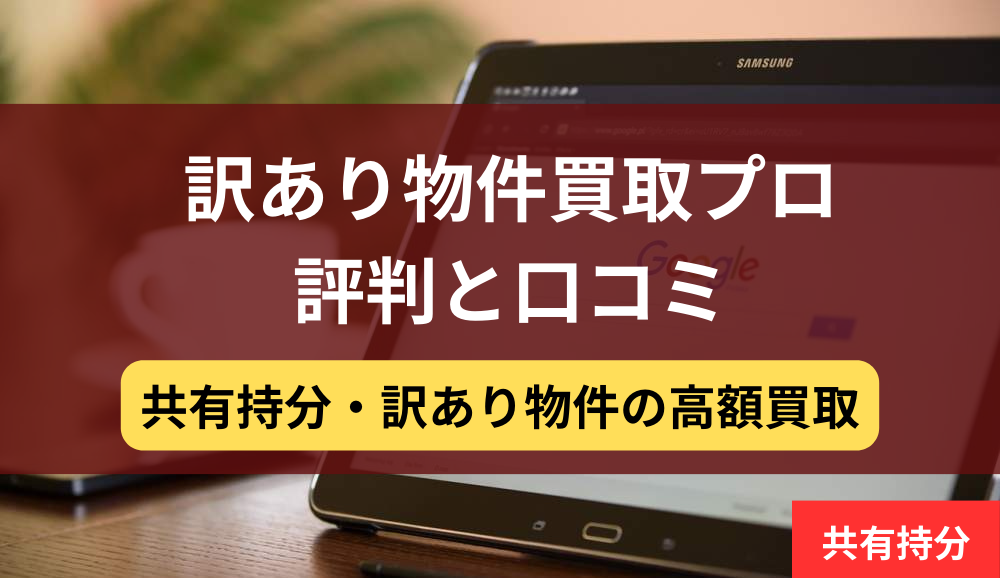亡くなった親の名義のままである家を売るには、所有者の名義を変更するための相続登記が必要です。
相続登記が事情でできない時や、他の相続人と共有となっている不動産の売却の同意が取れない時は、相続登記も同時に依頼ができる共有持分の売却という方法があります。

この記事では、通常の親名義の家を売る場合の手順の他に、相続登記ができない状態の親名義の家であっても売却できる方法の両方を解説します。
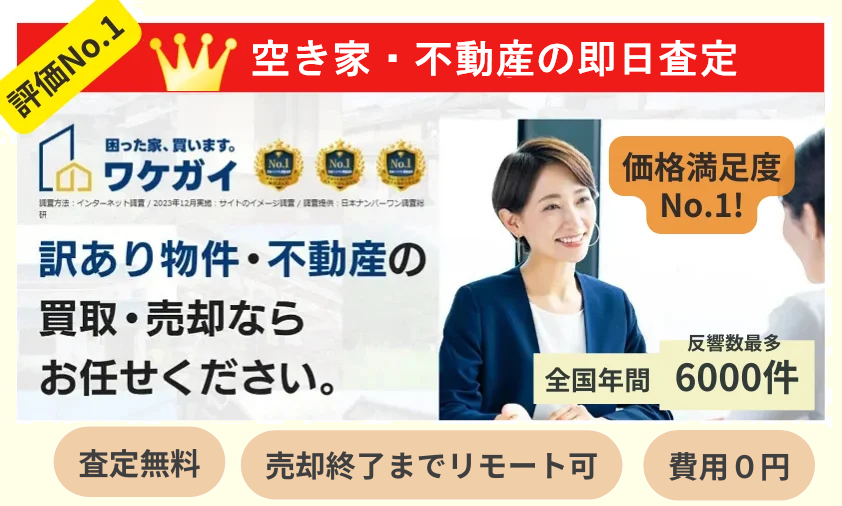
訳あり物件買取のワケガイは全国対応、共有持分の買取では業界最大手で、年間6,000件の相談件数は買取業者トップクラス、買取価格の満足度が高い評価No.1で信頼度の高い会社です。
ワケガイの査定は無料で買取金額を提示する即日スピード査定、、買取に至らなかった場合も費用は一切発生しないので安心して依頼できます。査定から売却終了まですべてリモート対応も可能です。
※ワケガイ詳細記事へ
ワケガイの評判・口コミ【訳あり物件買取・共有持分の最大手】
関連記事:
共有持分の買取業者おすすめランキング【2026年】
この記事でわかること
・亡くなった親名義の家を相続登記する方法
・共有者の同意なしに売れる共有持分の売却
関連記事
亡くなった親名義の家を売るには
親名義の家を売ろうとするもっとも最初に行うことは下の2つです。
親の家を売る準備
- 名義の確認
- 不動産の状況の確認の準備
- 相続人でそれなりの話し合いや意思確認があるとベスト
念のため名義の確認をする
通常、親が亡くなったときに親が所有する不動産は、親の名義で登記がなされています。
稀に祖父の名義であったり、親のどちらか一人、多くは父親など単独名義でなく、父親と母親、またはほかの親族と共有状態になっているなどの場合もあります。
両親が住んでいた家だからと言って、親の名義であるとは限りませんので、まず最初に名義を確認するところから始めましょう。
不動産の状態をチェック
また、念のために同時に不動産の状態を把握できればベストです。
近年の例では、売ろうとした実家が再建築不可物件であったという事例があります。
案外、不動産に名義以外の問題が見つかることもあります。雨漏りやシロアリもその筆頭です。
このような問題がある場合は不動産査定の金額に影響するため、見慣れている実家であっても、不動産の調査は意外に大切です。
不動産価格の注意点
売却の時に不動産店に査定してもらってもいいですが、近年は購入時と売却時の価格の乖離が大きくなっているため、推測は禁物です。
1千万円で売れると思ってきょうだいで争っていたら、実は数百万円だったということもあるためです。もちろんエリアによっても大きな違いがあります。
相続登記が売却に必須
親名義の家を売るにはまず、所有者の名義を変更するための相続登記が必要です。
相続人があなた一人であれば、そのまま売却手続きに進めます。
しかし、相続人が複数である場合は、親の家は実質的に共有名義と同じ扱いになります。
そのため、相続登記後でも、反対する相続人が一人でもいると売却ができません。
相続人であれば、自分の権利のある共有持分を自由に登記をすると同時に、他の相続人の法定相続分の登記を同時に行うことができます。
その後、自分の共有持分を売却できるため、親名義の家でも共有持分の売却なら現金化して手放すことができます。
親名義の家を売るにはまず、所有者の名義を変更するための相続登記が必要です。
相続人であれば、自分の権利のある共有持分を自由に登記をすると同時に、他の相続人の法定相続分の登記を同時に行うことができます。
親の家を売却する場合の通常の手順
まず、相続がスムーズに問題がなく進む場合の手順を示します。
1.相続手続きの確認
まず、家が相続財産であること、家屋や土地、それ以外の付属物の名義を確認しましょう。
2.相続人の決定
複数の相続人がいる場合、全員の同意が必要です。
相続人が決まっていない場合は、家屋を相続するための適切な手続きが必要です。
もし、どうしても共有者の同意が取れない場合ば、共有持分の売却という方法が取れます。
3.不動産の評価
不動産の価値を査定します。これには、地域の市場価値や物件の状態などが考慮されます。
不動産取引情報や、実際の周辺エリアの売買化価格などで自分で調べることもできますが、正確な金額は不動産業者に依頼をします。
この時点で、不動産業者を選ぶ作業を両方行うことになります。
4.不動産業者の選定
地元の信頼できる不動産業者を選びます。相続税や手続きに詳しい業者が望ましいです。
売却契約の締結: 不動産業者と売却契約を締結します。契約には、売却価格、売買条件、手数料などが含まれます。
5.契約の締結と手続
買い手が見つかり、売却条件が合意されたら、契約を締結します。売却代金の決済や不動産登記簿の更新などの手続きが行われます。
亡くなった親名義の家をそのまま売る方法
共有者がいる親名義の家で、共有者の意見が合わないなど相続登記ができないと、家は親の名義のままとなります。
その場合の、親名義のままの家をそのまま売る方法は以下の手順になります。
1.相続手続きを完了する
法定相続分の相続登記を行います。これにより不動産は相続人の共有名義となります。
2.共有持分の買取業者の選定
共有名義の不動産の場合は、通常の不動産店では依頼に応じてくれませんので、共有持分の買取業者を選びます。
3.共有持分の評価と査定
共有持分の買取業者に査定を依頼して、不動産の価値を査定し、市場価格を把握します。
3.契約の締結と手続
提示された価格での売却を決めたら、売買契約の締結を行います。売却代金の決済や不動産登記簿の更新などの手続きが行われます。
亡くなった親の家は相続登記が必要
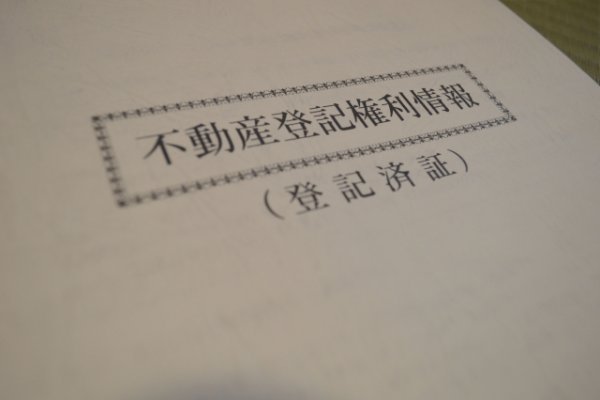
相続が生じたときには親の不動産は親が所有者であり、したがって親が名義人となっています。
相続後はこれを、家土地を相続する人の名前で登記しますが、それが相続登記と呼ばれるものです。
相続登記はなぜ必要?
亡くなった人の名義では、意思が確認できませんので不動産は売れません。
そのため所有者を明確にして登記を移転する必要があるのです。
相続登記は正確に言うと「相続による所有権の登記」のことです。
それまでの不動産の所有者が亡くなった場合に、その土地や建物の名義を亡くなった方から遺産をもらう人に変更する登記が相続登記です。
相続登記に必要な書類
相続登記は相続人が自分一人であるときは、単独でできますが、相続人が複数の場合には、共同で行うことが望ましいのです。
しかし、協力して相続登記ができない時は、誰かひとりの申請で登記をすることができます。
ただし、その際には、他の相続人の住民票、相続人との関係を示す戸籍謄本などが必要になります。
これらは、身内であっても自分以外の人の書類は取得ができませんので、司法書士に依頼することとなります。
以下に説明をする共有持分の売却の場合には、共有持分を買取する不動産会社は提携する司法書士がいるため、そちらに依頼をすれば相続登記を進めてもらえますので、書類の取得の心配はいりません。
亡くなった親の家を売る流れ

亡くなった親の家を売るには通常ならば、相続人同士で共同で相続登記を行います。
相続登記をするためには、もちろんその前に誰が実家を相続するのかを決めなければいけません。
相続登記に至るまでを含める手順は下のようになります。
- 遺産分割協議をする
↓ - 遺産分割協議書の書類作成
↓ - 書類をそろえる
↓ - 相続登記を依頼
↓ - 売却を依頼
↓ - 売却代金を受け取る
相続登記ができない時は、遺産分割協議がまとまらないか、または、被相続人が不在や音信不通などで話し合いができない場合が多いです。
なので、上記の行程の、いちばん最初のところから、売却に向けての動きがまったくできないこととなります。
話し合いがうまくいって、家を仲介で協力して売却する場合と、それができない場合のそれぞれのケースについて見ていきましょう。
親の家を仲介で売却する
上記が順調にいけば、相続登記が終わった不動産はもはや親の名義ではありませんで、相続人である子どもの名義になっているはずです。
亡くなった人の相続人が子どもが2人である場合、たとえばA男とB子がいる場合は、実家の相続方法は
- A男が家を相続する
- B子が家を相続する
- A男とB子の共有名義とする
の3つのうちのどれかになりますね。
共有名義の相続の意味
この最後の共有名義というのは、A男とB子の両方が実家を相続するという方法です。
必ずしも、両方がその実家に住むわけではなくても、後で売るにしてもその方が公平だからという理由で共有名義にされる方も多くいます。
両方の取り分が等分の半分ずつであった場合、共有名義なのでA男さんは実家全体ではなくて、「持分2分の1」を相続して所有しているということになります。
同じくB子さんも「持分2分の1」を相続して所有している状態です。
相続した家を売るには
A男が家を相続した場合は、家は既にA男さん名義であり、そのままA男さんが自分の財産として売ればいいのです。
B子さんが相続した場合も同じです。
最後の「A男とB子の共有名義とする」相続を選んだ場合には、名義は既にA男とB子の名義ですので、家を売る時も両方の連名で売るということになります。
親の名義の家はそのままでは売れない
それでは、何らかの原因でA男さんとB子さんが相続協議の話し合いができなかった、またはまとまらなかった場合はどうなるでしょうか。
たとえば、A男さんが音信不通であったり、何らかの重い病気で話し合いができなかったりしたケースなどです。
また、元々仲が悪いきょうだいだったのでけんかになって、どちらがもらうかということが決められなかった、相続登記そのものができなかったというケースです。
その場合は、家は親の名義のままですから、町の不動産店に行って相談すると
亡くなった人の名義の家は売れませんよ
と言われます。
しかし、実際には、亡くなった人の名義のままでも家は売れます。
それが共有持分の売却です。
共有持分の売却の手順
その場合の手順は下の2段階です。
- 亡くなった人の名義の不動産を法定相続分で相続登記をする
- 自分の持分を売却する
というものです。
1.相続登記をする
亡くなった人の名義の不動産は、名義変更をする相続登記ができないわけではありません。
亡くなった人の不動産も相続登記ができます。
ただしその際は上に説明したように、A男さんまたはB子さんが単独で相続するという相続のし方はできません。
それぞれが均等に法律で決められた権利分を共有名義で登記をするという方法のみになります。法律で決められた権利分は法定相続分と呼ばれます。
相続登記後の共有持分
相続登記を終えれば持分2分の1は A 男さんの所有です。
共有名義ではあっても、 A 男さんの持分に関してはA 男さんが名義人ですので、 A 男さんは自分の所有する不動産を自由に売買できます。
同じように、B子さんも、自分の持分についてはA男さんに関係なく売却することができます。
この持分の売却は私が弁護士の先生に教えてもらった方法ですので、けっしてあやしい危ない方法ではありません。
それによって亡くなった人名義の不動産であっても、法定相続分の登記を行って売ることができます。
この法定相続分の登記はA男さんの単独申請でできます。
つまり、いちいちB子さんに断る必要はありません。
自分一人でも自由に亡くなった親名義の不動産を売却することが可能です。
相続登記の単独申請について
相続登記の単独申請は共有者の住民票など、自分で取得することができないものが含まれますが、これは司法書士に依頼すれば行えます。
ただし、相続登記の単独申請は、依頼しても引き受けない司法書士もいます。
共有持分の売却の際は、業者に売却する業者買取となるため、信頼できる業者ならチームを組んでいる司法書士を手配し、相続登記を含めて移転登記と全部を一度に行えます。
相続登記を先に頼んで、次に売却の移転登記をまた頼むと言ったことをせずにすべてを一緒に同時に行うため登記費用もその分安く済むことが多いです。
共有持分の売却は、困ったときに役に立つ唯一の解決法ですので、ぜひ直接ご相談ください。
また、司法書士は書類の取得に不可欠のため、共有持分の買取業者は士業提携の専門の会社でそれなりに大きな会社に依頼することが、持分を高く売るコツとなります。
共有持分の買取会社は無料で弁護士相談が受けられるところもありますので、ぜひご利用ください。
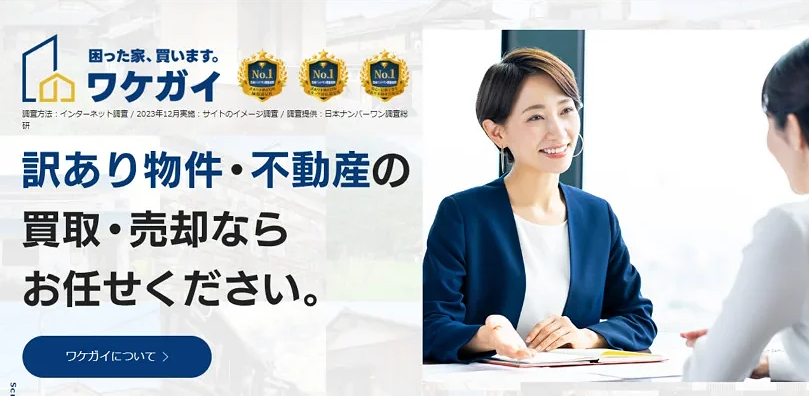
- 不動産高額買取⇒価格満足度Top
- 共有持分の業界最大手
- 買取率ほぼ100%
- 訳あり物件買取でNo.1の高評価
- 査定無料・全国対応
査定無料・全国対応